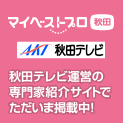2025年
7月
07日
月
開業13年!ありがとうございます!
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの土田です。
今日2025年7月7日で開業から13年となりました。
これも沢山の方々に支えて頂いてのことです。
本当にありがとうございます。
13年を振り返ると、開業前や開業してからも、様々な方に「秋田県で有料相談をする独立系FPは難しいよ」とか「東北なら仙台くらいの人口、経済規模でないと」など、沢山の否定的なアドバイスも頂きましたが、実際にその通りで最初の数年間は経営的にも厳しく、試行錯誤しながら何とかやってきたという印象でしたが、少しずつお客様も増え、経営的にもなんとか安定してきたところです。
秋田の独立系FP事務所が存続できた、その一因として外部環境の変化があります。
13年前は投資なんて一部の金持ちのもの、という印象が強く(今でもまだ根強いですが)、将来のために資産運用しましょうなどというと、詐欺師に思われるような時代でしたが、将来不安や政府の施策(NISAやidecoなど)によって、投資がより身近なものになりました。
身近になったとはいえ、投資の知識もなく始めるのは不安という方々からお問合せ頂くケースが増え、一気にお客様も増えてきました。この外部環境の変化がなければFPに相談しようという方ももっと少なかったであろうと感じております。
そしてクライアントが増えると、その他のFP業務の依頼も増えていきました。
多いのは相続系の相談、事業承継の相談で、事業承継からそのまま経営顧問をさせて頂くケースもあって、業務の幅がどんどん広がっています。顧問FPとしてクライアントから頼られることは大きな喜びであり、感謝の言葉と頂く度に、独立して本当に良かったと思います。
今後はFPとしての業務能力の向上は勿論ですが、クライアントのライフプランを実現するサポートという、FPの本懐を達するためにも、コーチングスキル(実は日本メンターコーチ協会にてトレーニングを受けております!)の向上や、経営者のクライアントにとってライフプランと一体の経営を含めたサポートするために、経営コンサルティングスキルの向上(こちらも経営コンサル塾の塾生として約4年間学んでおります!)を行って参ります。
これからも事業に関わる全ての方への感謝と、自己研鑽(自身の成長が顧客サービスの向上!)、そして人生を楽しむことも忘れずに精進して参りますので、今後とも「ライフ・デザイン・ラボ」をよろしくお願いいたします。
2025年7月7日 土田 茂
2025年
3月
14日
金
金が史上最高値更新!そして下落中の日本株が熱いワケ!海外投資家も注目する「宝の山」とは?
こんにちは!秋田のファイナンシャルプランナー土田です。
早いもので3月ももう半ば!2025年も1/4が終わろうとしていますが計画の進捗はいかがでしょうか?
さて、世界は常に変化していますが、今日の日経新聞記事から2つの記事を紹介します。
2025年3月14日 日経新聞Web版 「金3000ドル、20年で10倍「揺らぐ米ドル覇権」第3の波」
以下引用
金(ゴールド)の国際価格が史上初めて1トロイオンス3000ドルの大台を突破した。1970年代前半、2000年代後半に続く戦後3回目の高騰の波だ。背景には米ドルの覇権的な地位が揺らいでいることがある。国際政治が分断にさらされるなかで、実物資産としての金に行き場を失ったマネーが集中している。
引用終わり
2025年3月14日 日経ヴェリタス 「ジャパン・アズ・ナンバー2 日本株改革に賭ける海外勢」
以下引用
日本株には宝の山がある――。これは決して強がりではない。
手掛かりは、グローバル展開する大手資産運用会社の動きにある。米国初のミューチュアルファンド(投資信託)を101年前に始めた老舗の米MFSインベストメント・マネジメントは最近、15年ぶりに日本株の運用戦略を新規で立ち上げた。米アライアンス・バーンスタイン(AB)も約20年ぶりに新たな戦略での日本株運用を始めたという。
引用終わり
金価格が史上最高値更新!
まず、金の価格について。安全資産として知られる金ですが、その国際価格がなんと史上初めて1トロイオンス3000ドルを突破しました!背景には、米ドルの地位の揺らぎや地政学リスクの高まりがあると言われています。世界経済の不確実性が増す中で、投資家たちはより安定した資産を求めているんですね。
海外投資家が日本株に注目するワケ
一方で、日本株市場にも大きな変化が訪れています。海外の大手資産運用会社が、15年ぶり、20年ぶりに日本株の運用戦略を新たに始めたというニュースは、投資家の間で話題になっています。
なぜ今、日本株なのでしょうか?
- デフレからインフレへの転換: 企業が収益を上げやすい環境になってきたこと
- コーポレートガバナンス改革: 企業が株主を意識した経営へと変化していること
- ウォーレン・バフェット氏の投資: 著名投資家であるバフェット氏が日本の商社株への投資を拡大していること
これらの要因が、海外投資家にとって日本株市場が魅力的に映っているようです。
「This time is different(今回は違う)」
過去にも日本株ブームはありましたが、今回は企業の「実績」が伴っている点が大きく異なります。アベノミクス以降のコーポレートガバナンス改革が進み、海外投資家からは日本企業が着実に成長しているとみられているようです。
まとめ
直近の金価格の上昇は、世界経済の不安定さを物語っています。しかし、そんな中でも日本株市場は、海外投資家からの信頼を得て、新たな成長期を迎えようとしているかもしれません!
私たち個人投資家も、これらの情報をしっかりと把握し、時代に合った賢い投資判断をしていきたいですね。
賢い投資判断は自身のライフプランから始めて下さい!
ご相談はこちらからどうぞ。
今日もありがとうございました。
2025年
1月
24日
金
年金額が1.9%増加!でも実際は…
こんにちは、秋田のファイナンシャルプランナーの土田です。
今日は2025年の公的年金額が1.9%引き上げという発表がありましたので、それについてお伝えしますね。
年金額が増えるけど、実質的にはどうなの?
2025年度の公的年金の支給額が、2024年度から1.9%引き上げられることが発表されました。この増額は3年連続で、賃金や物価の伸びを反映した結果です。ただし、年金財政を維持するために導入されている「マクロ経済スライド」によって、賃金の伸び率(2.3%)から0.4%分引かれた1.9%が最終的な増加率となります。つまり、額面上では増えているものの、実質的には目減りしているということです。
年金の支給額はどのくらい増えるの?
たとえば、自営業者が加入する国民年金の場合、40年間保険料を納めた場合の満額は月6万9308円となり、2024年度から1308円増えます。一方、会社員などが加入する厚生年金では、夫婦2人の「モデル世帯」(夫が40年間働き、専業主婦の妻がいる場合)で月23万2784円となり、同じく4412円増えます。
また、働き方によって年金額は異なります。たとえば、平均月収が50.9万円で39.8年間厚生年金に加入した男性の場合、2025年度の年金額は月17万3457円で、3234円増えます。一方、平均月収が35.6万円で33.4年間加入した女性の場合は、月13万2117円で、2463円の増加となります。
マクロ経済スライドって何?
マクロ経済スライドは、将来の年金財政を安定させるための仕組みです。賃金や物価の伸び率から、「スライド調整率」というものを差し引くことで、年金の増加を抑えます。これにより、現役世代の負担が過剰にならないようにしています。
ただし、賃金や物価の伸びが小さい場合には、年金額が減らないように調整されます。一方で、賃金や物価が下がった場合は、その下落分だけ年金額が減る仕組みです。このようにして、年金の給付と負担のバランスを取ることが目的です。
老後の生活費をどう準備する?
年金だけでは、老後の生活費を十分にカバーできない可能性があります。特に物価が上がると、年金額が増えても購買力は減少するため、実質的な生活費が足りなくなることがあります。そのため、老後資金を準備する際には、インフレに強い資産を活用することが大切です。
たとえば、株式や投資信託、不動産などの資産は、インフレに強い特徴があります。これらを活用することで、老後の生活費を実質的に維持することができます。ただし、リスクも伴うため、自分に合った資産運用の方法を選ぶことが重要です。
自分のライフプランを考えよう
老後資金を準備する第一歩は、自分がどのような老後を送りたいかを考えることです。旅行を楽しみたいのか、趣味に没頭したいのか、それとも家族と穏やかに過ごしたいのか。それぞれの目標によって必要な資金は異なります。
その上で、ライフプランを立て、自分に合った手段を選びましょう。NISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)、証券投資に抵抗がある方なら積立型の保険など、さまざまな方法があります。無理のない範囲で計画的に資金を準備することが大切です。
まとめ
2025年度の年金額の増加は一見良いニュースですが、実質的な価値は減少していることに注意が必要です。老後の生活費を安定させるためには、年金だけに頼らず、インフレに強い資産を活用した資金準備が欠かせません。また、自分の理想の老後をイメージし、それに向けたライフプランを立てることが、安心した生活を送るための鍵となります。
ライフプランを立ててみたい!という方はこちらからどうぞ。
今日もありがとうございました。
2025年
1月
17日
金
トランプ大統領復活!金融市場で注目されている人物とは?
こんにちは、秋田のファイナンシャルプランナーの土田です。
いよいよ来週、アメリカの大統領にトランプ氏が返り咲きますね。
金融市場で注目されている人物には、財務長官に指名された、ヘッジファンド出身のベッセント氏がいます。
今回は金融市場への影響について、上昇要因と下降要因をまとめてみました。
トランプ大統領就任と金融市場への影響
上昇要因
- ベッセント氏の政策への期待感 トランプ政権で財務長官に指名されたスコット・ベッセント氏は、ヘッジファンド運用者としての実績が豊富で、その相場観に注目が集まっています。特に、“3-3-3政策”と呼ばれる財政赤字削減、成長率の引き上げ、原油増産を柱とした政策が実現すれば、株式市場やエネルギー市場にポジティブな影響を与える可能性があります。
- ドル基軸通貨としての地位の強調 ベッセント氏は公聴会でドルの基軸通貨としての地位を守る姿勢を明確にしました。この発言は、ドル買いを促進し、為替市場での安定性を高めると考えられています。
- インフレ鈍化による利下げ期待 直近の米消費者物価指数(CPI)と卸売物価指数(PPI)の上昇率が市場予想を下回ったことにより、FRBによる利下げの可能性が浮上しています。これにより、株式市場や不動産市場が恩恵を受ける可能性があります。
- 原油市場の期待 原油増産を含む政策はエネルギーセクターを活性化させる要因となり、関連銘柄への投資が活発化する可能性があります。
下落要因
- 中国への強硬姿勢 ベッセント氏は公聴会で中国を「歴史上もっともバランスを欠いた経済」と批判し、中国元を売る可能性を示唆しました。このような強硬姿勢は米中貿易摩擦を再燃させるリスクがあり、特にアジア市場における不安定要因となり得ます。
- 財務長官としての経験不足 ベッセント氏は公聴会で政治経験の不足を露呈し、金融政策や財政政策における判断能力に疑問を抱かれる場面がありました。市場参加者は、この点を懸念材料として捉えています。
- 追加関税の発効リスク トランプ大統領が予告している追加関税の発効や、それに伴う報復関税は、貿易関連銘柄や製造業セクターにネガティブな影響を及ぼす可能性があります。
- ヘッジファンドとの利益相反問題 ベッセント氏が財務長官に就任した場合、利益相反を避けるために運用資産を売却する必要がありますが、このプロセスが市場に混乱をもたらす可能性があります。
結論
トランプ大統領の就任は、金融市場にとって大きな転換点となる可能性があります。ベッセント氏の政策やFRBの金融政策が市場の方向性を左右する一方、中国との関係悪化や追加関税といったリスク要因にも注意が必要です。
このように、上昇要因、下降要因ともにあり、どう転ぶかは蓋を開けてみないことには分かりませんが、投資目的はライフプランを達成することなので、短期的な市場の変動に振り回されることなく、リスク分散を徹底し、中長期的な視点で投資戦略を検討することをお勧めします。
投資戦略も含めたライフプランを作成してみたい!という方はぜひご相談ください。
今日もありがとうございました。
2025年
1月
10日
金
民間の医療保険は必要?不要?
民間の医療保険は必要?不要?その判断のポイントを考える
秋田のファイナンシャルプランナーの土田です。
医療保険について、「加入すべき」という意見と「不要ではないか」という意見が対立する場面をよく目にします。それぞれの主張には理由があり、どちらが正しいとは一概に言えません。本記事では、民間医療保険の必要性についての論点を整理し、加入の目的を明確にする重要性についてお伝えします。
必要という意見の主な理由
-
予期せぬ医療費への備え 急な病気やケガで高額な医療費が発生した場合、公的保険だけではカバーしきれない費用が生じることがあります。特に、入院時の差額ベッド代や先進医療費は自己負担となるため、これらを補う民間保険が役立つとされています。
-
公的保険制度の改正による負担増加 日本の公的健康保険制度は改正を繰り返し、自己負担割合が増加傾向にあります。例えば、70歳以上の高齢者でも所得に応じて負担割合が2割や3割になる場合があり、将来的な制度変更を見据えて備えたいと考える人も多いです。
-
精神的な安心感 医療保険に加入していることで、予期せぬ事態への経済的な不安が軽減されるという心理的な効果も大きいです。
不要という意見の主な理由
-
公的保険制度が充実している 日本の公的保険制度は、世界的に見ても非常に優れています。高額療養費制度により、医療費の自己負担額には上限が設けられているため、過剰な保険料を支払う必要はないと考える人もいます。
-
貯蓄で対応可能 健康な生活を心がけ、資産形成を進めることで、医療費の自己負担分を十分に賄えると考える意見もあります。保険料を貯蓄や投資に回すことで、より柔軟に資金を活用できるという考え方です。
-
保険料のコストパフォーマンス 保険料を長期間支払い続けても、実際に保険金を受け取る機会が少ない場合、コストパフォーマンスが悪いと感じることがあります。
公的保険制度の改正と自己負担増加の傾向
日本の公的保険制度は、医療費の増加や少子高齢化に対応するため、たびたび改正されています。例えば、70歳以上の医療費負担割合の変更や、自己負担限度額の見直しが行われています。また、先進医療や差額ベッド代といった公的保険の対象外となる費用も増えており、自己負担額が高額になるケースが増えています。
民間医療保険は補完的な役割を
差額ベッド代や先進医療費など、公的保険ではカバーできない部分を民間医療保険で補うことは合理的です。しかし、必要以上に多くの保険に加入する必要はありません。自分がどのようなリスクに備えたいのかを明確にし、それに応じた保険を選ぶことが大切です。
資産形成の重要性
医療費の自己負担分を支払える状況を作るためには、日頃から資産形成を行うことが重要です。無理のない範囲で貯蓄や投資を進め、万が一の際に対応できる経済的な基盤を整えましょう。保険はあくまで補助的な手段と考え、資産形成とのバランスを取ることがポイントです。
まとめ
民間医療保険の必要性は、人それぞれの価値観や経済状況によって異なります。公的保険制度の現状や改正の動向を把握した上で、自分にとって必要な保障内容を見極めましょう。そして、資産形成を通じて、自己負担分をカバーできる経済的な余裕を持つことが、長期的な安心につながります。